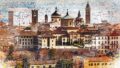みなさんこんにちは、Trio Strataです!
今回は、フランス近代の作曲家モーリス・ラヴェル(1875-1937)についての話題です。
ラヴェルは、その緻密な書法から、「スイスの時計職人のようだ」と言われていました。
彼の代表作としては、『亡き王女のためのパヴァーヌ』などが挙げられますね。
それでは、ここで問題!
Q.1 パヴァーヌとはどんな踊り?
- スペイン由来のゆったりと歩くような踊り

- 日本由来の先祖供養の行事で行われる踊り

- イギリス由来の軽快な踊り

![]() 正解!
正解!
![]() 不正解!
不正解!
スペイン由来のゆったりと歩くような踊り
スペイン由来の「パヴァーヌ」は16世紀〜17世紀頃、西洋の宮廷で流行しました。
イギリス由来の軽快な踊りは「ジーグ」、日本由来の先祖供養の行事で行われる踊りは「盆踊り」です!
ラヴェルはスペインの文化にも触れていた
ラヴェルはフランスを代表する作曲家ですが、出身はバスク地方シブールという街で、スペインとの国境に位置する場所なのです。
とても美しい港町で、ラヴェルもたびたび帰郷し、隣町のサン=ジャン=ド=リュズで海水浴を楽しんでいたそうです。
(かの有名なボレロもここで作曲されました!)
そのような環境で、幼少期からスペイン文化にも馴染み深かったラヴェルが、「パヴァーヌ」に着目したのは自然なことかもしれません。

「亡き王女」って誰のこと?
では、「亡き王女」とは一体誰のことなのでしょう?
原題には「infante」という言葉が使われており、これはスペイン王女の称号を意味します。
諸説ありますが…「亡き王女」は、1651年に生まれたマルガリータ・テレサ・デ・エスパーニャという王女に由来するようです。
スペイン画家ディエゴ・ベラスケスがマルガリータ王女の肖像画を遺しており、後にルーヴル美術館で鑑賞したラヴェルにインスピレーションを与えたと言われています。
つまりこの曲は、ラヴェルに近しい亡くなった王女の葬送ではなく、1枚の絵画から連想された「昔々スペインの王女様が踊っていたようなパヴァーヌ」
…と、雰囲気で付けられたタイトルなのです。
それでは最後に、丸尾編曲のトリオ版「亡き王女のためのパヴァーヌ」をお楽しみください!